角川春樹事務所の雑誌「ランティエ」で、
「横山雄二・吉村喜彦の世界」というタイトルで特集いただきました。

表4(ウラ表紙)は、
『酒の神さま』の宣伝になっています。

ぼくは、「酒のホネ」というエッセイを書かせてもらいました。
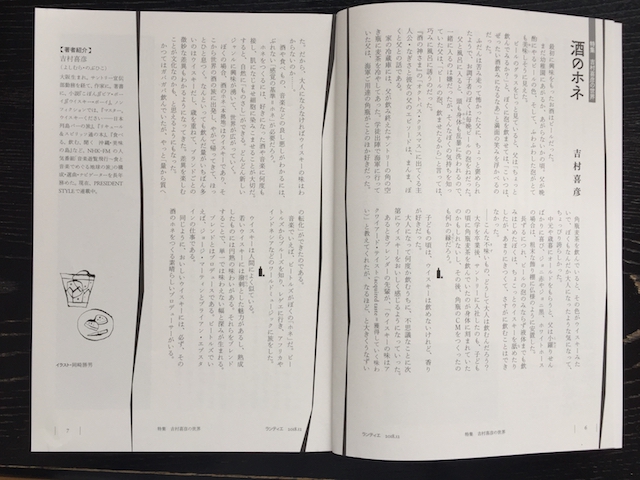
(内容)
_______________________________________________
「酒のホネ」
最初に興味をもったお酒はビールだった。
まだ幼稚園になるか、ならないかの頃。
父が晩酌にやるビールの色、そして、ふわふわした泡がとても美味しそうに見えた。
ビールのグラスをじっと見ていると、
父は「ちょっと飲んでみるか?」と、
ぼくに泡を飲ませては、「こいつは、ぜったい酒飲みになるなあ」
と満面の笑みを浮かべるのだった。
ふだんは苦み走って怖かった父に、ちょっと褒められたようで、
お調子者のぼくは毎晩ビールの泡をねだった。
父と風呂に入ると、頭もからだも乱暴に洗われるので、一緒に入るのは嫌だったが、
そんなぼくの気持ちを知っていた父は、
「ビールの泡、飲ませたるから」と言っては、巧みに風呂に誘うのだった。
『酒の神さま』の「オクトパス・クリスマス」に出てくる主人公・なぎさと彼女の父のエピソードは、
まんま、ぼくと父との話である。
家の冷蔵庫には、父が飲み終えたサントリーの角の空き瓶に麦茶を冷やしてあった。
学徒出陣で海軍に行っていた父は、海軍ご用達の角瓶がことのほか好きだった。
角瓶麦茶を飲んでいると、その色がウイスキーみたいで、
ぼくもなんだか大人になったような気になって、ちょっぴり誇らしかった。
中元や歳暮にオールドをもらうと、父は小躍りせんばかりに喜び、
ジョニ赤やジョニ黒、ホワイトホースの場合は、
粗末な飾り棚に仏様のように安置した。
長ずるにつれ、ビールの泡のみならず液体までも飲みはじめたぼくは、
ちょこっとウイスキーを舐めたりしたが、
あまりにきつくて、さすがに飲むことはできなかった。
───こんな不味いもの、どうして大人は飲むんだろう?
大学を卒業後、サントリーに入社したのも、
子どもの頃に角瓶麦茶を飲んでいたのが身体に刻まれていたのかもしれないし、
その後、角瓶のCMをつくったのも何かの縁(えにし)だろう。
* * *
子どもの頃は、ウイスキーは飲めないけれど、香りが好きだった。
大人になって何度か飲むうちに、
不思議なことに次第にウイスキーをおいしく感じるようになっていった。
あるときブレンダーの先輩が、
「ウイスキーの味はアクワイアード・テイスト(acquired taste=獲得していく味わい)」と教えてくれたが、
なるほど、と大きくうなずいた。
だから、大人にならなければウイスキーの味はわからないのか……。
酒や食べもの、音楽などの良し悪しがわかるには、
ぶれない「感覚の基準=ホネ」があるかどうかだろう。
ホネをつくるには、好きになった酒や音楽に何度も接し、
肌になじませ細胞に染みこませることが大切だ。
すると、自然に「ものさし」ができる。
どんどん新しいジャンルに興味が湧いて、世界が広がっていく。
ぼくの場合、酒のホネ(本拠地)はウイスキーであり、
そこから世界の酒の旅に出発し、やがて帰ってきて、ほっとひと息つく。
なんといっても飲んだ量がいちばん多いのはウイスキーだし、
歳を重ねて、ブランドごとの微妙な差異もわかるようになってきた。
差異を楽しむことが文化なのかも、と思えるようにもなった。
かつてはガバガバ飲んでいたが、
やっと「量から質への転化」ができたのである。
音楽でいえば、ビートルズがぼくの「ホネ」だ。
ビートルズからブルーズを知り、レゲエに行き、
アフリカやインドネシアなどのワールドミュージックに旅をした。
* * *
ウイスキーは人間によく似ている。
若いウイスキーには溌剌とした魅力があるし、
熟成したものには円やかな味わいがある。
それらをブレンドすることで、単一では味わえない幅と深みが生まれる。
ブレンドとはプロデュースである。
ビートルズでいえば、ジョージ・マーティンとブライアン・エプスタインの仕事である。
同じように、おいしいウイスキーには、
必ず、その酒のホネをつくる素晴らしいプロデューサーがいる。
________________________________________________
蔦屋家電の北田博充さんが「バー・リバーサイドの世界」を
書いてくださっています。
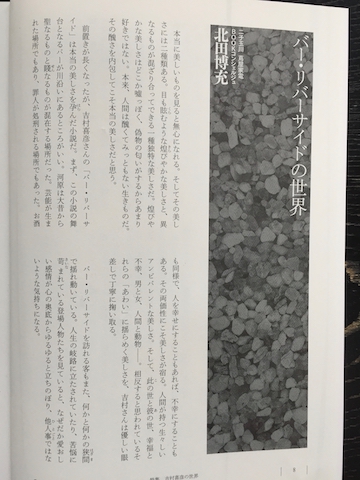
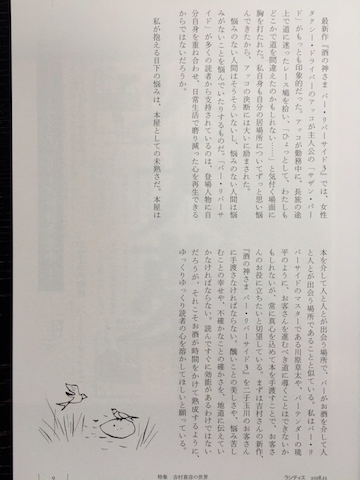
ご一読いただければ、うれしいです!

